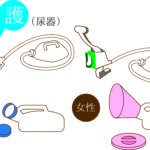リハビリ専門職必見!物事を伝える際のポイント③
会議やカンファレンスを通して、チームのメンバーに具体的な行動を提案することがあります。
しかし、「その場では納得してくれたはずなのに、なぜ行動してくれないんだろう…?」と悩むことはありませんか?
これはひょっとすると、相手に行動を促す内容が含まれていないのかもしれません。
物事の伝え方に気を使われている人は、
- 結論を述べる
- 理由を述べる
- 例を示す
- もう一度結論を述べる
といった順序でお話されることが多いかもしれません。
この順序自体には大きな問題が無く、話し手も聞き手も双方が頭の中を整理しやすいように思います。
ただ多くの場合、④の「もう一度結論を述べる」が単なる①の繰り返しになっている印象を受けます。
②③の内容が少々複雑であったり、長い解説にならざるを得ない場合は、①を再度繰り返すことで聞き手に「あぁ、そうだった」と結論を想起させることができるかもしれません。
結論がシンプルにまとめ上がっていれば、よりキャッチーに強調することにも繋がるでしょう。
いずれにせよ聞き手にとっては、(話し手が)していた話の輪郭が少しでも記憶に残りやすくなるかと思われます。
しかし、提案の目的が“相手に行動してほしい”場合、これでいいでしょうか?
結論において目標やゴールがいくら綺麗に示されたとしても、『具体的な行動内容』が共有されていなければ、うまくスタートは切れません。

ですので、④を『もう一度結論を述べる」から『これから何をするか』に変えてみましょう。
以下に例文を示します。
①相手に行動を促すには、具体的な行動内容を示す必要があります。(結論を述べる)
②ゴールは非常に大切です。しかしそこへ至るまでの行動内容も示されないと、メンバーはチームの中で何に・いつ・どのように取り掛かるべきか分からないからです。(理由を述べる)
③例えば「今期は対象者のADLをしっかりみていこう!」と言われても、具体的にすべきことが決まっていなければ、意識を持たせることしかできません。
しっかりみれたのか・みれていないのか判定できませんし、そもそも何をもってしっかりみれたとするのかが不明確なので行動に着手しようがありません。(例を示す)
④なので、まず「何を・いつ・誰が・どのように」行うか役割分担しましょう。(これから何をするか)
どうでしょうか?
簡易的な例文ではありますが、今まず自分に何が求められているか分かりやすくありませんか?
このように冒頭では『ゴール』を、結末では『行動 or 手段』を述べて同意を得ると、期待する行動が促されやすくなるかもしれません。
投稿者
浅田 健吾先生
株式会社colors of life 訪問看護ステーション彩

平成21年に関西医療技術専門学校を卒業し、作業療法士の免許取得する。
回復期・維持期の病院勤務を経て、令和元年より株式会社colors of life 訪問看護ステーション彩での勤務を開始する。
在宅におけるリハビリテーション業務に従事しながら、学会発表や同職種連携についての研究等も積極的に行っている。
大阪府作業療法士会では、地域局 中河内ブロック長や地域包括ケア委員を担当しており、東大阪市PT.OT.ST連絡協議会の理事も務めている。
平成30年からは、大阪府某市における自立支援型地域ケア会議に助言者として参加している。