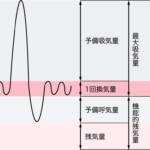リハビリ専門職必見!物事を伝える際のポイント①
対象者やご家族への説明
上司・先輩への報告
他職種との連携場面
カンファレンスやサービス担当者会議での意見交換など…
日々の業務の中で、相手に物事を伝えなければならない場面が多くあるかと思います。
しかし、
「話が長くて最後まで聞いていられない」
「結局のところ、何が言いたいの?」
「私に一体、何をしてほしいのか?」
このように言われて焦ってしまうことはありませんでしょうか?
うまく伝えたつもりでも
実は相手が“誤った理解をしていた”ということも珍しいことではないかと思います。
『相手に自分の考えを伝える』という行為は、うまく行おうとするととても難しいことです。
特に療法士は、「難しい言葉を並べてたくさん話すので、言っていることがよく分からない」といったご意見を寄せられることが多いと聞きます。

では、どういったポイントを押さえればいいでしょうか?
話し方の工夫はたくさん示されていますが、まずは会話を行うにあたって前提となるポイントを押さえるべきと考えます。
ここでは、3つのポイントを示します。
- 自分が期待するほど、相手は話を聞いていないことが多い。
⇒ そもそも、必ずしも相手が自分の話に100%耳を傾けてくれているとは限りません。
ぼんやりと違うことを考えているかもしれませんし
あなたへの質問や回答内容を考えていて話に集中しきれていないかもしれません。
たとえ話し手と聞き手の立場が明確である講義の場面であっても、同様のことは起こり得ます。
- 立場・興味・場面等によって、相手の聞く姿勢は変化する。
⇒ 聞き手の職種(専門性)は一体何でしょうか?
話し手と聞き手に共通言語はどの程度あるでしょうか?
飲み会のようなフランクな場でしょうか?会議やコンペのように次の行動を決めるための場でしょうか?
こうした複数の要素によって、聞き手がその話の中でフォーカスする部分は変わるはずです。
- その話の結論によって、受け取り方は異なる。
⇒ 話し手は、一体何を求められているでしょうか?
聞き手に何らかの行動を期待しているのでしょうか?ひとまず理解してもらうことが目的でしょうか?
両者は、そもそも何のためにその話をしているのでしょうか?
これらによって、話の組み立て方を考える必要があります。
こうしたポイントを考慮した上で、
『次の行動が明確に示されつつ、一定のインパクトを持ってシンプルに伝える』ということが、
相手に物事を伝えるうえでの広義の目標になると考えます。
投稿者
浅田 健吾先生
株式会社colors of life 訪問看護ステーション彩

平成21年に関西医療技術専門学校を卒業し、作業療法士の免許取得する。
回復期・維持期の病院勤務を経て、令和元年より株式会社colors of life 訪問看護ステーション彩での勤務を開始する。
在宅におけるリハビリテーション業務に従事しながら、学会発表や同職種連携についての研究等も積極的に行っている。
大阪府作業療法士会では、地域局 中河内ブロック長や地域包括ケア委員を担当しており、東大阪市PT.OT.ST連絡協議会の理事も務めている。
平成30年からは、大阪府某市における自立支援型地域ケア会議に助言者として参加している。