在宅支援の専門家 OT浅田健吾の臨床家ノート
-
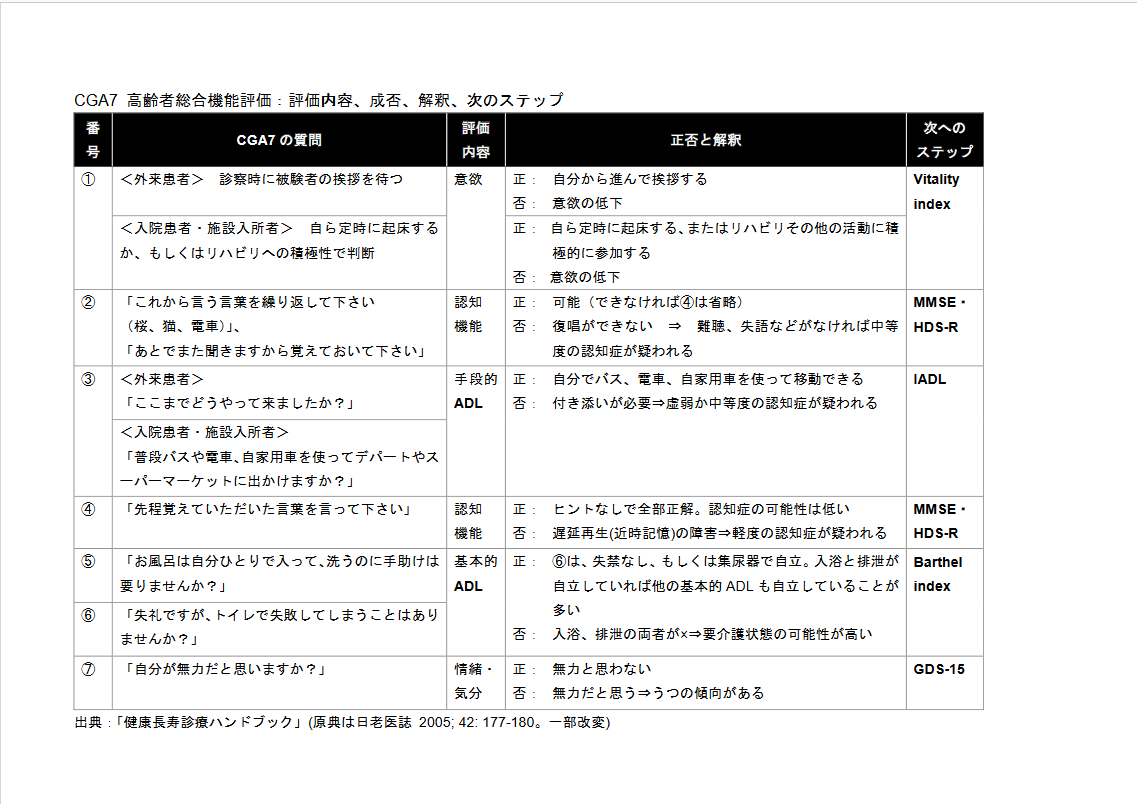 在宅における認知症利用者への対応のポイント
在宅における認知症利用者への対応のポイント
超高齢社会となり、在宅現場でも認知症を呈する方(もしくは認知症の発症が懸念される方)を対応する機会は非常に多いと思います。 今回は、認知症の方を対応するにあたってリハ職の皆さんが留意しておくべきポイントについて解説いたし […]
-
 在宅リハ評価 生活パターンの聞き取りの重要性
在宅リハ評価 生活パターンの聞き取りの重要性
対象者さんにどういった生活課題が存在するかを確認する目的で、生活パターンの評価はよく行われているかと思います。 今回は、そうした生活パターンの聞き取り時におけるポイント・注意点の確認です。 日常的なパターンであれば、朝 […]
-
 OT浅田健吾の臨床家ノート 在宅現場で意外と多く出くわすケース「退院当日における玄関アプローチの見落とし」
OT浅田健吾の臨床家ノート 在宅現場で意外と多く出くわすケース「退院当日における玄関アプローチの見落とし」
対象者さんの活動・参加に関わる動作で、“移動”についての評価を行う機会は非常に多いと思います。 ベッドからトイレまでの移動、自宅から社会参加の場までの移動といった“目的地までの移動”であったり、洗い場から浴槽への移動やレ […]
-
 OT浅田健吾の臨床家ノート 活動・参加レベルの目標設定の重要性
OT浅田健吾の臨床家ノート 活動・参加レベルの目標設定の重要性
患者さん・ご利用者さんのリハビリテーションの目標を活動・参加レベルで設定されることがあると思います。 特に回復期や生活期においては、そういった形での目標設定が望ましい・求められる風潮となっています。 では、なぜ活動・参加 […]
-
 OT浅田健吾の臨床家ノート 活動・参加の違いは?
OT浅田健吾の臨床家ノート 活動・参加の違いは?
日々の臨床において目標設定やプログラムを立案する中で、『活動・参加』を意識されることは多いと思います。 『活動(Activity)』とは、人間が生きていくうえで必要な個人レベルの行為を指します。代表的なものはADL(A […]
-
 OT浅田健吾の臨床家ノート 目標設定のポイント 活動・参加の支援方法
OT浅田健吾の臨床家ノート 目標設定のポイント 活動・参加の支援方法
病院であっても在宅支援であっても、リハビリテーションを展開する上で「活動・参加」というキーワードは昨今非常に良く耳にされるかと思います。 『リハビリテーションの展開と3つのアプローチ』という資料では「介護保険においては […]
-
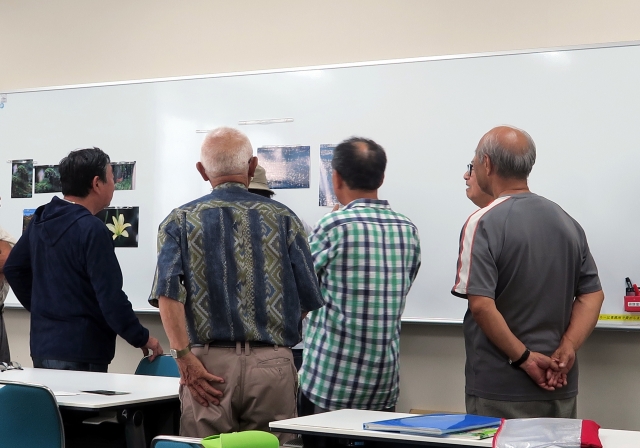 OT浅田健吾の臨床家ノート 目標設定のポイント 活動・参加を考える
OT浅田健吾の臨床家ノート 目標設定のポイント 活動・参加を考える
昨今よく耳にする『活動・参加』というキーワードは、目標設定にも関与します。 そもそも『活動・参加』が重要視される背景には、「回復の限界を十分考慮せず、心身機能へのアプローチによるリハビリテーションを漫然と提供し続けた場 […]
-
 OT浅田健吾の臨床家ノート 目標設定のポイント 対象者と設定する目標
OT浅田健吾の臨床家ノート 目標設定のポイント 対象者と設定する目標
皆さんは対象者の目標を、対象者本人と共に設定していますか? Maitraらよるとでは、対象者に目標についての説明を十分に行ったとする作業療法士が100パーセントに対し、作業療法の目標が全く分からないと答えた対象者は23 […]
-
 OT浅田健吾の臨床家ノート 目標設定のポイント 目標達成までの期間
OT浅田健吾の臨床家ノート 目標設定のポイント 目標達成までの期間
皆さんは患者・利用者と目標設定を行う際に、達成までの期間をどのように考えるでしょうか? 病院で勤務している方々は、退院まで期間で長期目標を設定し、その過程で複数の短期目標を設定される事が多いと思います。 一方、在宅領域 […]
